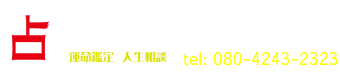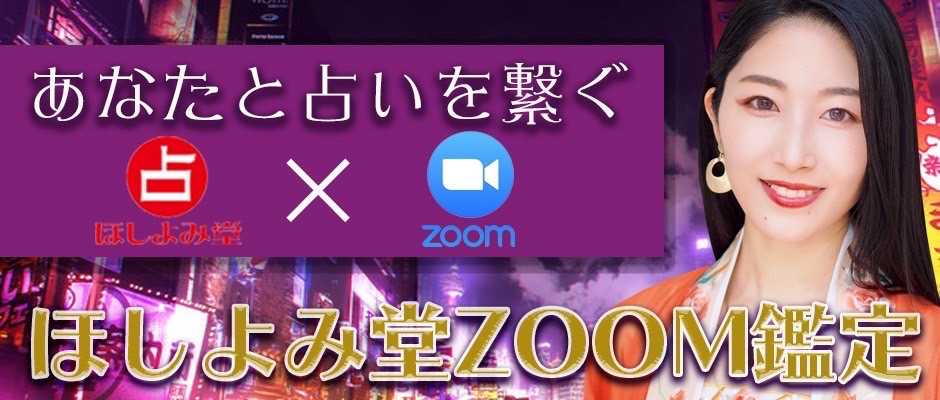ひな祭りは、「五節句(ごせっく)」の「上巳(じょうし)の節句」が由来
マリウス✨です
節分も終わり、来月は桃の節句、🎎ひな祭りですね
古代中国や日本では、季節の節目となる日を「節句」といいます。これは、奈良時代に中国から伝わったとされる暦で、季節の変わり目に次の季節を無事迎えられるよう、お祓いやお清めの行事・儀式を行う風習がありました。
春夏秋冬の四季が色濃くあり、稲作を中心とした生活リズムを培ってきた日本には、季節の変わり目となる節句がたくさんあったため、江戸時代の幕府が節句を5つに絞り、公的な行事や祝日として「五節句(ごせっく)」を定めました。
五節句は、1月7日の「人日(じんじつ)の節句」、3月3日の「上巳(じょうし)の節句」、5月5日の「端午(たんご)の節句」、7月7日の「七夕(しちせき)の節句」、9月9日の「重陽(ちょうよう)の節句」の5つ。
中でも、3月3日の上巳の節句は、川で身を清めたり、宮中で宴席を催すなどして災厄を祓う中国の習わしと、「禊祓(みそぎはらい)」の思想や「人形(ひとがた)」を流す日本の伝統文化が融合し、のちに雛人形を飾る「ひな祭り」となったといわれています。
ひな祭りが「桃の節句」と言われるのはなぜ?
また、ひな祭りが「桃の節供」ともいわれるのは、上巳の節句の季節に桃の花が咲いていたことや、古代中国では、邪気払いとして桃の花を清酒に浸した「桃花酒(とうかしゅ)」が飲まれていたためとされています。
日本では、江戸時代より、3月3日のひな祭りは、桃花酒に代わって「白酒(しろざけ)」が飲まれるようになりました。その理由は、大蛇を身ごもってしまった女性が白酒を飲んで胎内の大蛇を流したという説や、老舗酒屋が桃花酒の代わりに白酒を売り出したという説もあります。
ちなみに、現在のひな祭り(上巳の節句・桃の節句)以外にも、五節句の風習は残っています。
1月7日の「人日(じんじつ)の節句」には七草粥を食べて無病息災を願ったり、5月5日の「端午(たんご)の節句」は「こどもの日」として国民の祝日とされており、鯉のぼりを飾ったり、菖蒲湯に入ったり、柏餅やちまきを食べ、子供の健やかな成長を祈願します。
7月7日の「七夕(しちせき)の節句」は、七夕(たなばた)として、短冊に願い事を書いて笹の葉に吊るしたり、9月9日の「重陽(ちょうよう)の節句」は「菊の節句」とも呼ばれ、菊酒や栗飯を食べて不老長寿を願います。
なぜ3月3日がひな祭りなの?
ひな祭りは、五節句の2番目「上巳(じょうし)の節句」が由来ということは前述の通り。「上巳」は「じょうみ」とも読み、本来は「3月最初の巳(み)の日」という意味でした。
かつでの日本の日にちには、十二支(じゅうにし:子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥)が割り当てられていました。巳の日とは、そのなかでも「巳」に該当する日のことをいいます。
「上巳の節句」は3月の始めに来る巳の日でしたが、江戸時代の幕府が五節句を定めたことから、3月3日が上巳の節句とされ、以降も3月3日にひな祭りの行事が催されるようになった、といわれています。
ひな祭りは「邪気を祓う行事が発展したもの」、目的は「女の子の健康と幸福を祝う行事」
現代のひな祭りは「女の子の健康と幸福を祝う行事」です。しかし、ひな祭りの由来である「上巳の節句」を含む、季節の節目を意味する「節句」は、昔から邪気が入りやすい時期とされていました。
現代のひな祭りは、節目の日である節句に、邪気を祓う行事が発展したものだといわれています。
日本の行事には隠れた意味がある事が多いですね。。雛人形をお持ちの方は是非飾って、春を迎える準備と合わせて邪気祓をしてみましょう
マリウス