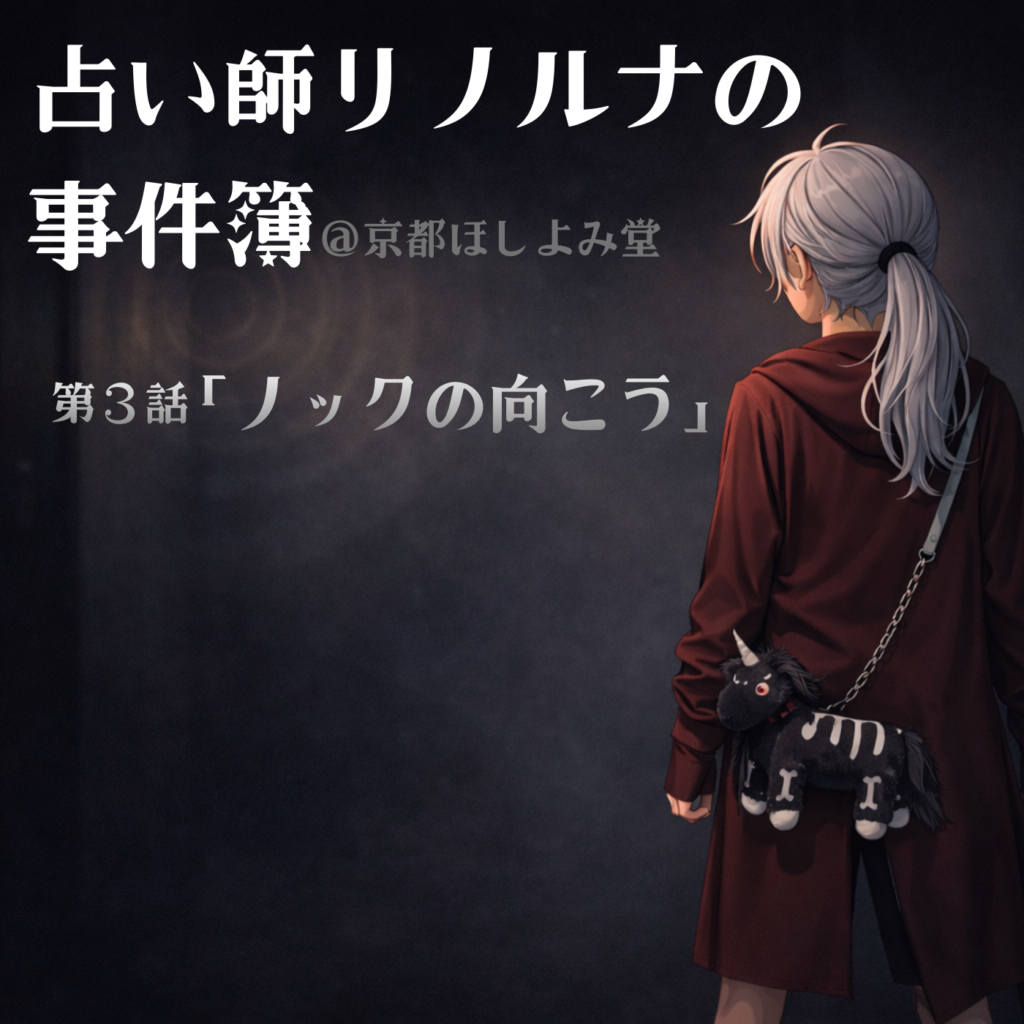
占い師リノルナの事件簿@京都ほしよみ堂③「ノックの向こう」
その男性客は、最初は占いを希望して予約を入れてきました。
ところが、店に入ってきた彼の様子は、どこかおぼつきません。
椅子を勧めて、向かい合い、
「さあ、何がありましたか」
そう声をかけた途端、彼は突然、泣き出しました。
「生まれてから、一度もうまくいったことがなくて……」
言葉が途切れ、しばらく嗚咽だけが続きます。
「最近は、どうやって死のうか、そればかり考えています。
でも、死ぬことすら、うまくできない。
どうして、こんな人生になってしまったのか……理由が知りたくて」
ぼくは何も言わず占星術の、術の作動を始めました。
ホロスコープを読み進めて、
ひとつ、強く引っかかる配置があります。
「隠された領域」に入ったリリス。
貪欲さと空白を示す星。
――憑依体質。
さらに過去を遡ると、
七歳の位置に水星がありました。
この場合、
情報と認識に歪みをもたらす星。
それ以外には、目立った異常はありません。
おかしい。
「本当に、あなたは生まれてからずっと、
うまくいかなかったと思っていますか?」
彼は、はっきりとうなずきました。
「母の言う通りに生きてきました。
田舎で、当時はネットもなくて、
学校も仕事も全部、母が決めました。
厄年には神社でお祓いもしました。
でも……周りから、馬鹿にされるんです。罵られる。
社会的には、それなりの立場にいるはずなのに」
社会的地位と、
現実の扱われ方が、まったく一致しない。
ぼくは、静かにサーチをかけました。
――いる。
彼の周囲に、
はっきりとした“別の気配”があります。
そして、それは七歳のころから、
彼に取り憑いたままだということも分かりました。
占星術の結果とも、
ぴったり一致します。
「あなたは、七歳のときから、
何かに取り憑かれたまま生きてきました」
彼の肩が、わずかに震えました。
「あなたの人生がうまくいかないと感じるのは、
あなたの身体を使って、
そいつが望む人生を歩いてきたからです」
その瞬間、
ぼくの中に、別の記憶がよぎりました。
――ぼくも、九歳だった。
「でも」
ぼくは、続けます。
「あなたは、本当にそいつに、
いなくなってほしいですか?」
彼は、顔を上げて、
はっきりと言いました。
「もう、うんざりなんです。
先生、追い払ってください」
意思は、確認できました。
「分かりました。お祓いをします。
終わるまで、リラックスしていてください」
ぼくは彼の傍らに立ち、
動作を始めます。
意識を緩め、
同時に集中させる。
力の流れを整える。
ぼくは、意識をさらに沈めました。
力を集め、
流れを一点に絞ります。
――コン、コン。
最初は、遠慮がちな音でした。
――コン、コン、コン。
次第に、規則的になる。
やがて、
――ドン。
一段、重たい音に変わりました。
ドン、ドン。
「……すみません」
ドアの向こうから、
男の声が聞こえます。
「開けてください。
約束の時間に遅れてしまって」
声は丁寧で、
どこか困ったようでもありました。
依頼人が、
不安そうにこちらを見上げます。
「あの……誰か来たみたいですけど」
ぼくは、視線を逸らさずに答えました。
「聞こえますか。
あれは“来客”ではありません」
ドン、ドン、ドン。
今度は、
少し焦りが混じります。
「すみません。遠くから来たんです」
「給湯器の件で呼ばれていて」
「ここを開けてもらえないと、困るんですが」
言葉が、やけに具体的でした。
生活の匂いがする。
――だからこそ、厄介だ。
「お祓いの最中は、
よくこうやって“お邪魔”が入るんです」
ぼくは、静かに言いました。
「大丈夫です。ぼくは中断しません」
ドン、ドン、ドン、ドン。
音が荒くなり、
叩く位置が、少しずつズレていく。
まるで、
どこを叩けば“通れる”のか、
探しているようでした。
そいつは、
依頼人の頭部に根を張り、
そこから内側へ入り込んでいます。
ここに、変更を加えます。
意味を、切り離す。
通路を、成立しないものにする。
――ドン。
最後の一撃は、
どこか苛立ちを含んだ音でした。
そして、
ぴたりと、止みました。
「終わりました。
これから、エネルギーを調整します」
ぼくが手を向けた瞬間、
彼は突然、大きな嗚咽を上げ、
鑑定台に突っ伏しました。
それでも、
ぼくは動作を止めません。
「……終わりました」
しばらくして、
彼は顔を上げました。
「温かい……。
全然、違います」
「いま、どんなお気持ちですか?」
彼は少し考えてから、言いました。
「……怒りしか、ありません」
ぼくは、うなずきます。
「それでいいんです。
怒りは、あなたがあなたに戻った証です」
彼は、ゆっくりと深呼吸をしました。
この怒りは、
壊すためのものじゃない。
戻るためのものだ。
ぼくは、そう確信していました。





