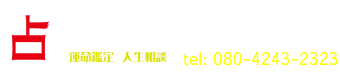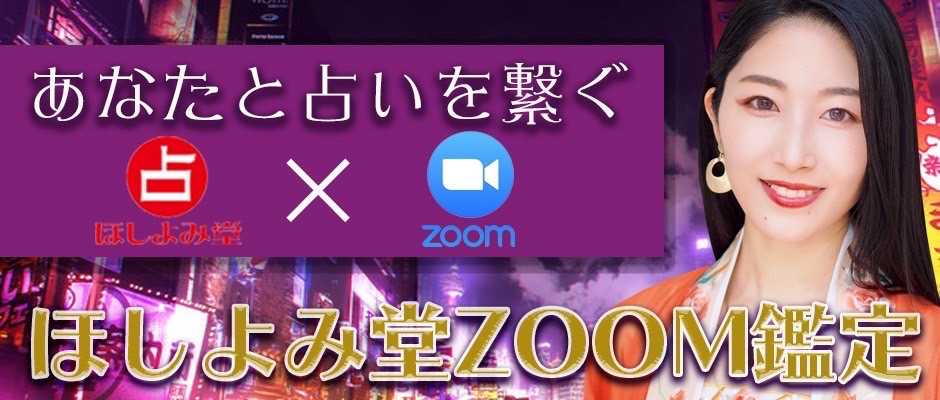マリウス✨です
1月10日頃になると、京都の街は一気に賑やかになります。それは、商売繁盛の神様として知られる恵比寿様を祀る「十日恵比寿祭り」の季節だからです。
京都の祇園四条近くの恵比寿神社では、毎年多くの人々が訪れ、福を呼び込むための「福笹」を授かります。
福笹の意味と縁起物の飾り
この福笹は、ただの笹の葉ではありません。竹のように真っ直ぐ伸びることから、繁栄や成長を象徴しています。また、笹に飾りをつけることで、さらにご利益を得るとされています。
恵比寿神社では、さまざまな縁起物を笹に飾り付けることができます。例えば、
• 鯛:大漁や成功を象徴
• 小判:金運を高める
• 米俵:豊作を願う
これらを笹に結ぶことで、その年の運気をさらにアップさせると言われています。
京都の「残り福」の文化
十日恵比寿祭りのもう一つの魅力は**「残り福」**の文化です。
祭りの最終日には、まだ福を授かっていない人たちに「残り物には福がある」という考え方で、残った福笹が授けられます。
京都の人々は、この「最後まで諦めず、粘り強く努力すること」にも価値を見出してきたのです。
耳が遠い恵比寿様に「トントン」と
京都の恵比寿神社には、他の場所にはない面白い参拝方法があります。それは、恵比寿様に願いが届くように壁を叩くことです。
恵比寿様は耳が遠いと言われています。そのため、お賽銭を入れてお願いをした後、神社の裏手に回って壁をトントンと叩くのが京都流。
このユニークな風習には、願いをしっかり届けたいという人々の素直な気持ちが込められています。
いかがでしたか?チャンスがあれば、ぜひ京都の恵比寿さまにお詣りくださいね
マリウス